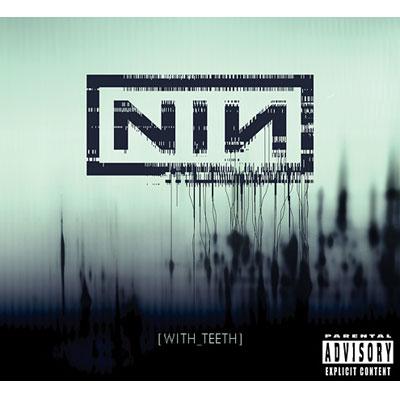
その後間をそれほどおかずにそれ以前のアルバムも全て揃えたのであるが、ネット上ではNINとしての活動はもうしないのではないか、というような噂があった気がする。
当時、自分の人生にこれほど深く入り込んできたバンドがその時点で既に生で見る機会がないと思ったとき、ひどく落胆したのを覚えている。
その頃はまだLuna Seaなんかも聴いていたけど、このバンドも解散したし、筋肉少女帯なんかも解散していたし、自分の好きになるバンドで現役のものは当時はあまりいなかったな。
それはともかく、それでも向こう何年かは過去の音源でも十分に越せるくらい聴いていた。
ライヴ盤なんかも買ったものだから、もうたまらないよね。
毎日聴いていたもの。
スタジオ盤とはまったくといっていいほど異なるサウンドに、痺れたね。
それゆえますますライヴへの渇望が強くなる訳である。
大学に進学して、ある友人と出会う。
彼は今に至も親交のある数少ない友人の一人になる訳であるが、彼もまたオルタナ系好んで聴いており、NINを知っている人に初めてであった喜びに震えたものだ。
本当に回りにはいなかったんですよ。
その友人から、不意にある時「ナインインチ新譜出すよ」と聴いて、大変驚いたね。
家にはインターネット環境がなかったし、当時はまだそんなに雑誌も熱心に読んでいなかったので。
で、調べたら確かに出ている。
5年ぶりの新作、とね。
タイトルは当時はまだ暫定段階であったと思うが、一体どんなアルバムなのかと待ちに待った。
先行シングルも聴いてなかったので、アルバムの発売がまさに初遭遇であったのである。
その友人と学校帰りにアルバムを買って帰り、内で黙って聴いていたのを良く覚えている。
第一印象としては、やはりかなり驚いた。
一方で、やっぱりな、という思いもあった。
というのも、当時次のアルバムの音に関して自分なりに予測していたムードにばっちりハマったからである。
かなり聴き込んでいたし、インタビューなんかもちらほら読んでいたので、そこからどういう音になるかと考えていたんですね。
まあそれはいいとして、でもやはりNine Inch Nailsの音源としては賛否両論になるんじゃないかな、という気はしたね。
実際「The Fragile」的世界観からどっぷりハマって行った口なので、あの軽快と言うか、肩の力の抜けた音には戸惑いもありましたよ。
一方で、歌詞に目を向けてもそうだったし、数回聴いてみればまごう事なきNINの音楽だとわかる。
でも、今までにない、聴いていて高揚するようなトラックまであったのは、やはり大きな変化である。
1曲目はかなり静かな展開ながら、空気が軽い。
音が軽い、という事でなくて、今までのような閉塞感がないのである。
風通しが良い、というかな。
色んなレビューにもあったが、ヴォーカルもはっきりしているしね。
2曲目は高速のドラムロールから始る。
デイヴ・グロール参戦のこの曲である。
このアルバムのこれらの仕事を通じて、それまで叩いていたジェロームとの仲が拗れてしまったという話もあるが、曲は文句なくかっこいい。
また、当時この曲の歌詞を観て、「やっぱりNINは俺には特別かもな」と思ったものだ。
3曲目も、これまた今までにない感じの曲であった。
正直この曲はあまり好きではないが、歌詞としては興味深いものがあった。
当時、トレント自身が今までの自分を振り返るような内容とも読める。
この内容を勘案すれば、このアルバムがこういう音になったのもうなずけるだろう。
続く"The Hand That Feeds"が先行シングルにもなった曲で、NIN史上初と言えるほどの縦ノリな曲。
そしてこのあとの彼の音楽に対する精神も端的に現れている1曲である。
「飼い主の手に噛み付くか、それとも跪くか」と迫る歌詞には、当時のアメリカ社会に対するメッセージが込められている。
ブッシュ政権下でイラク戦争、9.11テロというその後の世界情勢に多大な影響を与えた出来事を目の当たりにして、それまで自分の内側にばかり向いていた目が世界に向き始めたようである。
実際トレントは、あのワールドセンタービルの倒壊を目の当たりにしたアメリカ人の一人である。
変わらずにはいられなかった、という方が確かかもしれない。
そして、他の者にも突きつける。
変化か、傍観か。
この曲はライヴでも盛り上がるし、歌詞の内容も大好きである。
後期NINの一つの象徴ともいえる曲であろう。
何度聴いても胸が高鳴る思いがする。
その後は比較的重たい曲が続き、今までのNINファンもなんとなく懐かしさすら覚えるような。
しかし、それでもかつてのような緻密さというよりは、もっとダイナミックな印象ではあるが。
タイトル曲の歌唱法も随分と異なり、やはり歌がフィーチャーされたアルバムなんだろうと思うのである。
で、中盤にさしかかってまたかなり印象の異なる曲が入る。
"Only"である。
シングルカットもされたが、この曲はすごく好きである。
「There is no you, there is only me」というフレーズが印象的な曲で、これもまた多様に解釈できるだろう。
もう一人の自分という存在に対して、あるいは自分の存在を映す鏡のような存在としての他者とかね。
それまで目の前にあって、自分を苦しめたり、悩ませたりした存在というのは、実は最初からいなかったんじゃないのか、なんて唄われている。
自分の的な自分が作る、なんていう話もあるが、そんな印象を受ける。
曲としても、ある意味非常にシンプルで、テンポもミドル。
だけどすごく高揚するものもある。
ライヴだと、ムードを変えるのにすごく効果的である。
最新のライヴDVD「Beside You In Time」では、スクリーンの照明効果と相まって非常に幻想的でデジタルな世界観を作り出していた。
必見である。
次にはアルバム中最も速い"Getting Smaller"という曲が続く。
ある意味では軽い曲で、これはこれで珍しい。
その次の"Sunspot"も、あんまりないタイプの曲で、奇妙に気怠い感じの、真夏の太陽を見上げるような音像である。
次の"The Line Begins To Blur"は、またメタリックな感触の重たい曲。
この曲の歌詞は現実に直面したときの動揺のようなものが比較的ストレートに表現されており、このアルバムにかき立てられた要因を表しているようにも感じられる。
次の曲が実はアルバム中一番好きであったりする。
ライヴ盤タイトルにもなった曲。
なんというか、歌詞の内容がすごく外を向いていて、音自体にも希望すら感じる。
夜の高速道路を猛スピードで飛ばしたときに見える景色は、きっとこんな景色なんじゃないか、なんて思うよね。
駆け抜けて行くような感覚がなんとも気持ちのいい曲である。
そしてラストがアコースティックな感触の"Right Where It Belongs"。
現実とヴァーチャルの境界であったり、テレビの向こうとこっちであったり、ともすればどちらが現実なのかわからなくなってしまうような多次元的な現実のなかで、人々は自分に取って都合のいいものを現実とし捉えようとする。
そんな態度が今の世界の状況を招いたともいえ、それに対して、いい加減現実をみろ、とでも言っているかのようだ。
このアルバム全編通じて、抽象的になるとか、曖昧になるといった表現が使われる。
それに類する表現であったり、それをほのめかすような表現が随所に使われている。
現実と、自分の中の世界との境界、あるいは自分と世界との境界というのは時にひどく曖昧で、どちらが本当なのか、あるいはいま目の前にある事象というの実在しているのか、それとも自分が作り出した虚像なのかがわからないような気分になることも。
それは現実をきちんと直視してないからなのか、あるいは現実があまりに馬鹿げすぎていて、自分の想像の方がよほど現実的に思えるからなのか。
今の世の中というのは信じられない出来事のほうが遥かに多い。
現実離れしているからなのか、あるいは文字通り信じられないだけなのかはわからないが、いずれにしろもはや現実というのは身をゆだねられるほど安心な代物ではないし、夢に見るような幸せなんて与えてくれない。
それでも、今行きている現実こそが現実であって、それを直視せずにはもはやいられないはずである。
以降の活動でも、あるいはインタビューでも顕著であるが、そうした現実に向き合ってゆけ、というメッセージを発し始める。
一方で彼の表現の在り方も変わってゆく。
解放されたかのごとくに、精力的な活動をしてゆく訳であるが・・・。
ともあれ、色んな意味で非常に興味深いアルバムである。
いま聞き返すと尚更面白い。
やっぱりトレント・レズナーは最高だね、と思わせてくれる名作である。